西福寺古墳|矢上川左岸に築かれた梶ヶ谷古墳群の一つ
西福寺古墳の概要
西福寺古墳は、川崎市高津区にある名所旧跡です。西福寺古墳は、矢上川左岸に築かれた梶ヶ谷古墳群の一つで、直径35m、幅6〜7.5mの周溝からなる円墳です。昭和57年の発掘調査により、6世紀中以降の築造と考えられ、水鳥を模した埴輪なども発掘されたといいます。

| 名称 | 西福寺古墳 |
|---|---|
| みどころ | 神奈川県指定史跡 |
| 入場時間 | - |
| 入場料 | - |
| 住所 | 川崎市高津区梶ケ谷3-17梶ヶ谷第3公園 |
| 備考 | - |
西福寺古墳の由緒
西福寺古墳は、矢上川左岸に築かれた梶ヶ谷古墳群の一つで、直径35m、幅6〜7.5mの周溝からなる円墳です。昭和57年の発掘調査により、6世紀中以降の築造と考えられ、水鳥を模した埴輪なども発掘されたといいます。
新編武蔵風土記稿による西福寺古墳について
(梶ヶ谷村)
塚二ヶ所
一は北の方にあり、西福寺の持、四畝二十四歩許の所なり、又一も同邊にあり、ただ塚とのみ云て其ゆへを傳へず。(新編武蔵風土記稿より)
川崎市教育委員会掲示による西福寺古墳について
西福寺古墳
西福寺古墳は、矢上川左岸に築かれた高塚古墳群の中にあって、規模が大きく、保存状態も極めて良好です。
昭和五七(一九八二)年、古墳の景観整備の一環で行われた発掘調査の結果、この古墳が築かれたのは、六世紀中頃から後半と考えられ、直径約三十五メートル、高さ約五・五メートルの円墳で、墳丘の周囲には幅六~七・五メートル、深さ約八十センチの溝(コンクリートブロックで舗装されている部分)がめぐらされていたことがわかりました。
また出土した埴輪の中には、水鳥を模した埴輪の頭部も発見されています。
現在の西福寺古墳は、その成果に基づいて復元・整備をされたもので、昭和五五(一九八〇)年九月一六日、神奈川県史跡に指定されています。(川崎市教育委員会掲示より)
西福寺古墳の周辺図
参考資料
- 新編武蔵風土記稿
- 神奈川県神社誌

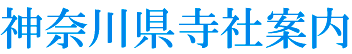
 西福寺古墳入口
西福寺古墳入口