磯部東日枝神社。下磯部東地区の鎮守
磯部東日枝神社の概要
日枝神社は、相模原市南区磯部にある神社です。磯部東日枝神社の創建年代等は不詳ながら、延文元年(1356)以前より下磯部東地区の鎮守として祀られていたといいます。

| 社号 | 日枝神社 |
|---|---|
| 祭神 | 大山咋命 |
| 合祀 | - |
| 境内社 | 稲荷神社 |
| 祭日 | 例大祭4月21日 |
| 住所 | 相模原市南区磯部1114 |
| 備考 | - |
磯部東日枝神社の由緒
磯部東日枝神社の創建年代等は不詳ながら、延文元年(1356)以前より下磯部東地区の鎮守として祀られていたといいます。
新編相模国風土記稿による磯部東日枝神社の由緒
(磯部村)
山王社二(新編相模国風土記稿より)
「さがみはら風土記稿」による磯部東日枝神社の由緒
下磯部の東講中によってまつられる神社です。
四ツ谷の日枝神社との関係は深く、ともに江戸期には「山王権現」と称され、文久元年(1861)の再建、慶応元年(1865)の改築、明治30年の修理などほぼ同時期に行っています。しかしその後の改修などは段々独自に行うようになり、その関係も薄れてきたようです。ちなみに昭和54年には境内の整備と社殿の新築を行っています。
参道の石段は53段あり、幕末に氏子が馬で運んできたといわれています。(「さがみはら風土記稿」より)
神奈川県神社誌による磯部東日枝神社の由緒
創立年月日は不詳であるが、延文元年(一三五六)以前より下磯部東地区の村の鎮守として、御神徳を追念するもの多く、江戸時代は別名山王大権現と称した。文久元年(一八六一)八月三十一日に社殿を再建し、慶応元年(一八六一)九月、社殿の再建をし、幟等も新しく調えた。境内地には樹木も多く、延長約二十メートルの石段は、幕末に氏子の人々が馬にて運んで築いたものである。明治三十年九月、社殿を新改築、更に昭和二年三月十六日に社殿を再び改築した。
昭和十四年四月三十日、鳥居を新築したが、昭和五十三年十二月に破損により再建。昭和五十四年七月、社殿の老朽に伴い新改築を計画し、氏子の奉納により昭和五十五年四月二十日に新しい社殿が完成。又石段、鳥居、参道等については株式会社相模土建を始め有志の奉納により整備され、面白を一新した。(神奈川県神社誌より)
磯部東日枝神社の周辺図
参考資料
- 新編相模国風土記稿
- さがみはら風土記稿
- 神奈川県神社誌

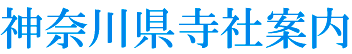
 磯部東日枝神社鳥居
磯部東日枝神社鳥居 境内社稲荷社
境内社稲荷社