熊野神社。浄明寺地区の鎮守、旧村社
熊野神社の概要
熊野神社は、創建年代は不詳ですが、応永年間(1394-1427年)及び永正年間(1504-1520)に社殿を再建したと伝えられ、隣接する浄妙寺が文治4年(1188)密教寺院として創建していることから、文治4年(1188)頃には創建されたものと推定できます。明治6年には浄明寺地区の鎮守として村社に列格していました。

| 社号 | 熊野神社 |
|---|---|
| 祭神 | 天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命 |
| 相殿 | - |
| 境内社 | - |
| 祭日 | 夏祭り:数年おきの7月 |
| 住所 | 鎌倉市浄明寺3-8-55 |
| 備考 | 浄明寺地区の鎮守、旧村社 |
熊野神社の由緒
熊野神社の創建年代は不詳ですが、応永年間(1394-1427年)及び永正年間(1504-1520)に社殿を再建したと伝えられ、隣接する浄妙寺が文治4年(1188)密教寺院として創建し、鎌足稲荷神社と共に当社も浄妙寺の鎮守としていることから、文治4年(1188)頃には創建されたものと推定できます。明治6年には浄明寺地区の鎮守として村社に列格していました。
境内掲示による熊野神社の由緒
相模風土記稿に「熊野神社は村の鎮守なり」と記録されてあります。このお宮は古くから浄明寺地区の氏神様として信仰されてきました。
社伝によれば応永年間(1394-1427年)及び永正年間(1504-1520)に社殿を再建したと伝えられています。明治6年(1873)には国より正式に浄明寺地区の鎮守として公認され、昭和27年には宗教法人として登記され現在にいたりました。
祭神は、天宇須女命、伊弉諾命、伊弉册命の三柱です。
7月の祭礼(夏祭り)には神楽が奏されますが、「湯花神楽」「鎌倉神楽」といわれ、地元の人々から愛されていました。然し最近では数年おきにおこなっています。火の神水の神を招神して感謝し、除災招福を祈り弓矢の威力で悪魔調伏を行います。(境内掲示より)
新編相模国風土記稿による熊野神社の由緒
泉水ヶ谷字東之澤寶生庵跡の東にあり。此谷を御坊と云ふ、村の鎮守なり。(新編相模国風土記稿より)
神奈川県神社誌による熊野神社の由緒
社伝によれば応永年間(一三九四~一四二八)及び永正年間(一五〇四~一五二二)に社殿を再建したという。
『相模風土記』に「熊野社、泉水ケ谷字東之沢安生庵跡の東にあり、此の谷を御坊と云う、村の鎮守なり」とある。社蔵の棟札に「文久三突未(一八六三)星春二月二十一日吉昭宿社殿再建しとある。明治四年九月神奈川県庁に提出された『鶴岡八幡宮一社明細書貼写しの「末社」0項に「熊野社浄明寺にあり」、また「建物世代洒幕府御普請所に御座候」とある。明治六年十二月村社に列格された。浄明寺区の氏神社である。(神奈川県神社より)
熊野神社所蔵の文化財
- 文久3年(1863)再建の棟札
- 嘉永7年(1854)の社号扁額
熊野神社の周辺図

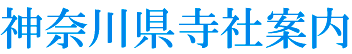
 熊野神社参道
熊野神社参道