押立神社|山城国稲荷大神の分霊を鎮祭し多摩川のあたりに鎮座
押立神社の概要
押立神社は府中市押立町にある神社です。押立神社は、慶長年間(1596-1615)山城国稲荷大神の分霊を鎮祭し多摩川のあたりに鎮座していたといいます。のち正保年間(1644-1648)洪水のため社地流失し当地に遷座し、手津久里稲荷と称していたといい、明治14年押立神社と改称したといいます。

| 社号 | 押立神社 |
|---|---|
| 祭神 | 稲蒼魂命 |
| 相殿 | - |
| 境内社 | 四社神社 |
| 住所 | 府中市押立町4-31-15 |
| 祭日 | 9月15日 |
| 備考 | - |
押立神社の由緒
押立神社は、慶長年間(1596-1615)山城国稲荷大神の分霊を鎮祭し多摩川のあたりに鎮座していたといいます。のち正保年間(1644-1648)洪水のため社地流失し当地に遷座し、手津久里稲荷と称していたといい、明治14年押立神社と改称したといいます。
新編武蔵風土記稿による押立神社の由緒
(押立村)
神明社
除地、長五十六間、幅三間、小名向嶋にあり、わづかなる祠にて、村内龍光寺の持なり。
稲荷社
字原新田にあり、本山修験玉泉院の持なり。
稲荷社
除地、五間に十間許、小名本村にあり、拝殿二間に二間半東向、内に五尺の宮作あり、村の鎮守、祭禮九月十九日、別當玉泉院。
神明社
小名本村にあり、小祠(新編武蔵風土記稿より)
東京都神社名鑑による押立神社の由緒
慶長年間(一五九六-一六一五)山城国稲荷大神の分霊を鎮祭し奉り、当初は玉川のあたりに鎮座。のち正保年間(一六四四-四八)洪水のため社地ことごとく流失した。よって現今の地に遷座し、手津久里稲荷と称し、農民こぞって尊崇した。領主高林弥一郎が社殿を改築。明治十四年五月押立神社と改称、翌十五年社殿を改築、有栖川一品親王殿下の御染筆による社号を額面として下賜される。(東京都神社名鑑より)
境内掲示による押立神社の由緒
慶長年間に、山城国稲荷大神(現在の京都伏見稲荷大社)の分霊を鎮祭したのが創建。当初は、現在の多摩川の辺に鎮座していたが、正保年間の大洪水のため現在の社地に遷座したという。万葉の昔から「てつくりの里」と歌われた土地柄ゆえに、手津久里稲荷と称し、村民挙げて尊崇し、殊に府中領初代代官高林弥一郎尊崇の余り、社殿を改築するに至ったと伝える。
明治十四年に押立神社と改称し、翌十五年には村民挙って社殿を改築し、大いに旧観を改め、有栖川宮一品親王殿下、特に押立神社の四字を御染筆額面として下賜せられた。
祭事は二月に初午祭、九月に例大祭を執り行なう。(北多摩神道青年会掲示より)
押立神社の周辺図
参考資料
- 新編武蔵風土記稿
- 東京都神社名鑑

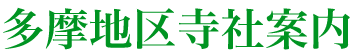
 押立神社鳥居
押立神社鳥居 押立神社境内社
押立神社境内社