第六天塚古墳|古墳時代中期築造
第六天塚古墳の概要
第六天塚古墳は、世田谷区喜多見にある史跡で、喜多見古墳群の一つです。第六天塚古墳は、直径28.6m、高さ2.7mの古墳で、古墳時代中期(五世紀末)に造られたといいます。

| 名称 | 第六天塚古墳 |
|---|---|
| みどころ | - |
| 区分 | 史跡 |
| 住所 | 世田谷区喜多見4-3 |
| 備考 | 喜多見古墳群の一つ |
第六天塚古墳
第六天塚古墳は、直径28.6m、高さ2.7mの古墳で、古墳時代中期(五世紀末)に造られたといいます。
世田谷区教育委員会掲示による第六天塚古墳について
古墳時代中期(五世紀末)と昭和五十六年(一九八一)の世田谷区教育委員会掲示による、墳丘及び周溝の調査によって、古墳の規模と埋葬施設の存在が確認された。
これにより、本古墳は、直径二十八・六メートル高さ二・七メートルの墳丘を有し、周囲に上端幅六・八〜七・四メートル下端幅五・二メートル〜六・七メートル深さ五十〜八十センチの周溝が廻り、その内側にテラスを有し、これらを含めた古墳の直径は三十二〜三十三メートルとなることが判明した。またこの調査の際に、多数の円筒埴輪片が発見された。
埋葬施設は、墳頂下六十〜七十センチの位置に、長さ四メートル幅一・一〜一・四メートルの範囲で、磔の存在が確認されていることから礫槨ないし磔床であると思われる。
なお同古墳については、「新編武蔵風土記稿」によると、江戸時代後期には第六天が祭られ、松の大木が生えていたとの記載が見られる。
この松の木は大正時代に伐採されたが、その際に中世陶器の壷と鉄刀が発見されており、同墳が中世の塚として再利用されていたということも考えられる。(世田谷区教育委員会掲示より)
新編武蔵風土記稿による第六天塚古墳について
(喜多見村)天神塚
前の続きにあり、高さ五尺許、塚上に天神牛頭天王の小祠を二つたつ。東向なり。(新編武蔵風土記稿より)
第六天塚古墳の周辺図

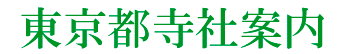
 第六天塚古墳
第六天塚古墳