日圓山妙法寺|厄除祖師
妙法寺の概要
日蓮宗寺院の妙法寺は、日圓山と号します。妙法寺は、元和年間(1615-1623)、真言宗径覚が日蓮宗に改宗して覚仙日逕と称し、寺名を妙法寺と改め、母日圓尼の菩提のため日圓山として開山したのを開創とします。祖師像は、もと碑文谷法華寺(現円融寺)でまつられていたものの、碑文谷法華寺が日蓮宗から天台宗に改宗させられた際に当寺へ譲られたもので、厄除祖師と称され、遠近よりの参詣も多く著名です。

| 山号 | 日圓山 |
|---|---|
| 院号 | - |
| 寺号 | 妙法寺 |
| 住所 | 杉並区堀ノ内3-48-8 |
| 本尊 | 十界曼荼羅 |
| 宗派 | 日蓮宗 |
| 葬儀・墓地 | 妙法寺堀之内静堂 |
| 備考 | 厄除祖師 |
妙法寺の縁起
妙法寺は、元和年間(1615-1623)、真言宗径覚が日蓮宗に改宗して覚仙日逕と称し、寺名を妙法寺と改め、母日圓尼の菩提のため日圓山として開山したのを開創とします。祖師像は、もと碑文谷法華寺(現円融寺)でまつられていたものの、碑文谷法華寺が日蓮宗から天台宗に改宗させられた際に当寺へ譲られたもので、厄除祖師と称され、遠近よりの参詣も多く著名です。
境内掲示による妙法寺の縁起
本寺院は日円山と号し、日蓮宗の寺で十界曼荼羅と祖師象が祀られています。開基は不明ですが、中興開山は妙仙院日円といい、元和七年(一六二一)寂したと伝えられています。
寺伝によれば、祖師堂の日蓮像は、日蓮聖人が四十二歳の時法難にあい伊豆に流された折、同行を許されなかった日朗上人が、鎌倉の岸辺に流れ着いた霊木を得て、祖師の御影を刻んだものと言われております。その後、目黒の法華寺からこの寺に移され、俗に「堀の内厄除祖師」として信仰されてきました。十一代将軍徳川家斉や十二代家慶が当書院に立寄って休息されたことから、いっそう有名になりました。
毎月の十三日、二十三日は縁日です。とくに元旦、節分会、八月の千部会、三月、九月施餓鬼会、十月の御会式には、江戸初期から善男善女、文人墨客で境内は足の踏み場もない程の賑わいで、浅草観音と並び称せられたと古書に記されています。
現在当寺には、国指定重要文化財の鉄門をはじめ、都指定有形文化財の祖師堂、書院、仁王門、麻布油絵日蓮上人像、その他仏像、絵馬堂、文人の碑など多くの文化財が保存されております。(杉並区教育委員会掲示より)
「杉並の寺院」による妙法寺の縁起
「妙法寺由緒書」等によれば、元和年間(1615-1623)、真言宗径覚が日蓮宗に改宗して覚仙日逕と称し、寺名を妙法寺と改め、母日圓尼の菩提のため日圓山として開山したのが当寺の開創と伝えている。
江戸初期に目黒碑文谷の法華寺(現天台宗円融寺)の末寺となるが、元禄11年、幕府による日蓮宗不受不施派弾圧により、法華寺が天台宗に改宗させられてよりは身延山久遠寺末となった。当寺を有名にした日蓮聖人像「厄除祖師」は、その折に法華寺より移されたものである。
この像は、弘長元年(1261)の伊豆配流に同行を許されなかった弟子日朗が師日蓮上人を偲んで彫り、二年後赦されて鎌倉に還った上人が開眼したと伝えられるもので、時に上人42才であったところから「厄除祖師」と喧伝され、信仰を集めた。
都文化財の書院は、「御成りの間」とも呼ばれ、11代将軍家斉・12代家慶が野遊の折に度々休息したとする記録があるが近世書院建築としても見事なものである。
国重要文化財の鉄門は、鋳・鍛鉄で作られ、装飾に鋳銅を使用した和洋折衷様式の大鉄門で、明治初期としてはまことに珍しい建造物である。(「杉並の寺院」より)
新編武蔵風土記稿による妙法寺の縁起
(堀之内村)妙法寺
除地、四百五十坪餘、抱添地四千二百三十八坪、境内都而四千六百八十八坪、日蓮宗甲斐國身延山久遠寺末開山妙仙院日圓元和七年十一月十日示寂す、此僧の名を以て日圓山と號せり、當寺往古は眞言宗なりしが、元和の初今の宗旨に改めたりと、明和六年丙丁の災に罹りて舊記を失ひ、詳なることを傳へずと云、本尊三寶諸尊四天王を安す、その中に持國・毘沙門の二点は運慶の作なりと云、木の立像長七寸、又祖師日蓮の木像あり、本堂は表門の正面にあつて十四間に十三間南向へり、其餘庫裡及び座敷向等甍をならべて造れり、
位牌堂。本堂の奥にあり、三間に一間半、
祖師堂。十一間に十八間瓦葺、向拝五間に三間銅瓦葺樓門の正面に建り、上人の木體は祖師四十二歳の肖像を、高足の弟子日朗靈木をもて彫刻せしものにて、除尼祖師と稱す、坐像にて長二尺九寸、厨子に入れり、もとは荏原郡碑文谷村法華寺(現天台宗円融寺)に有しものなりしが、元禄十一年九月かの寺の十八世日附の時妙榮といへる尼の事につき破戒の罪に處せられて遠流せられ、改宗あつて天台宗となりしにより此木像をば當寺へ譲りしと云、この比までは庵室の如くいとかすかなることにて有しが、其後靈驗世にあらはれ参詣引もきらず、立願の者力を極て土木の費を供せしによりて、次第に結構美をつくし、今はいよいよ繁榮せり、
寺寶
曼荼羅二幅。日蓮の眞跡なりと云、
身延山之記一幅。同筆なりと云、
法華經。序品方便品、
一巻。尊圓法親王の筆なりと云ふ、
同分別功徳品一巻。光明皇后の御筆なりと云、
法華經化城喩品一巻。菅家の筆なりと云、
同從地湧出品一巻。小野道風の筆なりといふ、
大黒天一軀。傳教大師の作と云、臼に乗れる木の坐像にて長七寸、
同一軀。自然石なり、立體にて長七寸、
摩利支天一軀。定朝の作なりと云、猪に乗れる坐像にて長一寸八分、
朝師堂。本堂の後にあり、三間四方、身延山久遠寺十一世の僧日朝の木坐像長五寸なるを安す、
額堂。二間に十八間、樓門を入て左の方にあり、こゝに攝待の茶場を張て、参詣のもの憩息のたすけとなせり、
鐘樓。一丈四方、樓門を入て左の方にあり、鐘のわたり二尺五寸、長五尺三寸、享保十年に鑄しものなり、
稲荷祠。書院の庭にあり、境内の鎮守なり、三尺に一尺五寸の祠、神體は長五寸の木像なり、
樓門。二間半に七間南向なり、祖師堂を距ること二十町許にあり、此餘同じ、並びに表門長屋裏門など號する門あり、
惣門。樓門を距ること十七間餘にたてり、(新編武蔵風土記稿より)
妙法寺所蔵の文化財
- 鉄門(国指定重要文化財)
- 麻布油絵日蓮聖人像(東京都指定文化財)
- 木像如来形坐像一体(杉並区指定文化財)
- 妙法寺旧参道入口灯籠一対(杉並区指定文化財)
- 明恵上人書状一軸(杉並区指定文化財)
- 絹本着色舞楽図六曲屏風一双(杉並区指定文化財)
- 本阿弥光悦和歌巻・同断簡二点(杉並区指定文化財)
- 乾山焼色絵花唐草文水注(杉並区指定文化財)
- 板絵着色老翁奇瑞の図一面(北渓筆)(杉並区指定文化財)
木像如来形坐像一体
応永四年(1397)に大檀那以下数名の立願により仏所式部法端によって造られた像高27.1㎝の小像で、日蓮宗の一塔両尊本尊中の一体が遺存したものと思われます。造立年代は妙法寺の創建より古く、伝来の由来も不詳ですが、素朴な地方作として、区内現存の木造諸像のうち造像銘を有する古仏として貴重な仏像です。(杉並区教育委員会掲示より)
妙法寺旧参道入口灯籠一対
和田三丁目五四番・五五番にある総高5.65mの青銅製の燈籠で、明治43年に花柳界の人々を中心とした信者の寄進によって造立されたものです。明治22年の中野駅の開業以降、新たな参詣道となった中野駅からの道に参道入口の標識として造立されたものです。妙法寺の信仰の廣さを証すると共に、参道口の変遷をも示す資料です。(杉並区教育委員会掲示より)
明恵上人書状一軸
鎌倉時代初期の高僧で華厳宗中興の祖といわれた明恵(1173-1232)の消息を掛軸装にしたものです。切紙に文五行を記したこの書状では喫茶にもふれており、明恵が茶種を栂尾で栽培したという話を裏づけています。鎌倉文化を代表する高僧の墨跡として、また、茶の栽培に関する初期の史料としても貴重な遺品です。(杉並区教育委員会掲示より)
乾山焼色絵花唐草文水注一口
尾形乾山(1663-1743)が焼いた高さ13.1㎝の水さしで、鳴滝窯時代(1699-1712)の作と思われます。一見磁器と思わす完好品で、銅部の赤絵の花文様に簡略化した「花唐草文」を描いた本水注は、中国明代景徳鎮窯呉須赤絵写の数少ない作例で、京焼及び江戸時代中期の陶芸と知る上できわめて貴重なものです。(杉並区教育委員会掲示より)
本阿弥光悦和歌巻・同断簡二点
「寛永の三筆」と謳われた本阿弥光悦(1558-1637)によるもので、元は一巻でしたが現在は巻子本(長さ885㎝)と掛軸に改装されています。具引き白地に「新古今和歌集」の巻第四秋歌上の和歌計十五首を順に書いており、その豊麗な書風は光悦の書風が完成する慶長期の特徴をよく示しています。(杉並区教育委員会掲示より)
板絵着色老翁奇瑞の図一面(北渓筆)
文政四年(1821)に奉納された横約2m、縦1.2mの大絵馬で、作者は葛飾北斎の高弟魚屋北渓です。図柄は日蓮宗信者の奇瑞にまつわる場面を描いてあります。主人公とおぼしき初老の男の面貌は葛飾北斎晩年の肖像と重なるところがあります。妙法寺の庶民信仰を示すとともに、浮世絵師魚屋北渓の有年紀作品としても貴重です。(杉並区教育委員会掲示より)
絹本着色舞楽図六曲屏風一双
「春鶯囀」「打毬楽」などの一二種の舞楽をやまと絵の手法で屏風の各扇に一つずつ描いたものです。舞楽図が景観の一部から絵の主題へと変化する過渡期である室町時代末期の作品として珍しいだけでなく、近世に廃絶した舞楽の所作や装束などが描かれていることから、図譜としても貴重なものです。(杉並区教育委員会掲示より)
妙法寺の周辺図

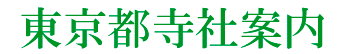
 妙法寺仁王門
妙法寺仁王門 妙法寺本堂
妙法寺本堂 妙法寺鐘楼
妙法寺鐘楼 妙法寺日朝堂
妙法寺日朝堂 妙法寺二十三夜堂
妙法寺二十三夜堂 妙法寺浄行堂
妙法寺浄行堂 妙法寺書院
妙法寺書院 妙法寺堀之内静堂
妙法寺堀之内静堂