秋葉神社(昆陽神社)|千葉市花見川区幕張町の神社
秋葉神社(昆陽神社)の概要
秋葉神社(昆陽神社)は、千葉市にある神社です。秋葉神社の創建年代等は不詳ですが、境内社昆陽神社は、甘藷栽培に成功した青木昆陽を祀る社として著名で、弘化3年(1846)に創建したといいます。

| 社号 | 秋葉神社 |
|---|---|
| 祭神 | - |
| 相殿 | 昆陽神社 |
| 末社 | - |
| 住所 | 千葉市花見川区幕張町4-803 |
| 備考 | - |
秋葉神社(昆陽神社)の由緒
秋葉神社の創建年代等は不詳ですが、境内社昆陽神社は、甘藷栽培に成功した青木昆陽を祀る社として著名で、弘化3年(1846)に創建したといいます。
稿本千葉県誌による昆陽神社の由緒
昆陽神社
同町大字馬加字北寺口に在り、秋葉神社の境内に属す。傳へ云ふ、青木昆陽琉球より甘藷の種を輸して之を本村に試植し、里民に其の培養法を授く、爾後郡中に繁殖し、天明年中四年飢饉の時之に因りて其の禍を免れたり、里民其の徳を追慕し、弘化三年三月其の霊を祀れりと。(稿本千葉県誌より)
秋葉神社(昆陽神社)所蔵の文化財
- 青木昆陽甘藷試作地
青木昆陽甘藷試作地
青木昆陽甘藷試作地
この地は、享保20年(1735)八代将軍吉宗の命により、青木昆陽が薩摩芋を試験栽培し、成功した所です。
昆陽は江戸日本橋の魚商の子で本名を文蔵と称し、京都で儒学を伊東東涯に学びました。江戸に帰ったのち町奉行大岡越前守に抜擢され、幕府書物方に登用され古文書調査・蘭学研究に励む一方「藩薯考」を著し甘藷栽培を説き、救荒食として飢饉に備えるよう吉宗に上書し認められました。甘藷は小石川養生園(現植物園)、下総馬加村(現在地)、上総豊海(九十九里町)で試作されましたが、現在地のみが成功しました。
甘藷栽培を紹介した人は昆陽以前にもいましたが、関東地方に広めたのは昆陽が最初であり、幕府の事業として実施したため全国に影響を与えました。その後幕府における甘藷栽培は次第に増え、天明の大飢饉にも甘藷のおかげで餓死者は皆無であったと伝えています。天保年間(1830-40)には、検見川で甘藷から飴も製造されるようになりました。(千葉市教育委員会掲示よより)
秋葉神社(昆陽神社)の周辺図

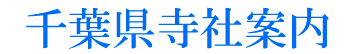
 秋葉神社鳥居
秋葉神社鳥居 昆陽神社
昆陽神社 秋葉神社石塔群
秋葉神社石塔群 道路向いの青木昆陽墓
道路向いの青木昆陽墓 青木昆陽墓
青木昆陽墓