寶積寺|市原市門前にある曹洞宗寺院
寶積寺の概要
市原市門前にある曹洞宗寺院の寶積寺は、玉泉山と号します。寶積寺は、延元年間(1336-1340)に雲叟瑞大和尚が臨済宗寺院として開山、挺庵正宗禅師(明応9年1500年寂)が曹洞宗寺院に改めて中興開山したといいます。徳川家康が関東入国した翌年の天正19年(1591)には寺領7石の御朱印状を受領、末寺6ヶ寺を擁していました。

| 山号 | 玉泉山 |
|---|---|
| 院号 | - |
| 寺号 | 寶積寺 |
| 住所 | 市原市門前2-220 |
| 宗派 | 曹洞宗 |
| 葬儀・墓地 | - |
| 備考 | - |
寶積寺の縁起
寶積寺は、延元年間(1336-1340)に雲叟瑞大和尚が臨済宗寺院として開山、挺庵正宗禅師(明応9年1500年寂)が曹洞宗寺院に改めて中興開山したといいます。徳川家康が関東入国した翌年の天正19年(1591)には寺領7石の御朱印状を受領、末寺6ヶ寺を擁していました。
「市原市史」による寶積寺の縁起
宝積寺(郡本)
延元年中雲叟瑞大和尚創建。天正十九年(一五九一)十一月朱印高七石をうける。元禄四年(一六九一)造立の石造千手観音がある。(「市原市史」より)
「市原郡誌」による寶積寺の縁起
玉泉山寶積寺
本郡郡本にあり、曹洞宗にして君津郡眞如寺末にして末寺六ヶ寺を有する小本寺格なり、延元年間(皇紀一九九六年頃)の創立にして、開闢開山は雲叟瑞大和尚禅師にして中興開山挺庵正宗禅師に明應九年一月(皇紀二一六〇年)遷化せらる、又左馬頭基氏公は開基信徒にして戒名瑞泉寺殿玉岸折光大居士貞治六年四月二十六日逝く、元は臨済宗なりしが挺庵正宗大和尚より曹洞宗となりしなり、徳川家康公より朱印七石寄附該、朱印は明治維新の際現境内千三百二十七坪を除き上地し、明治八年逓減禄下附せらる、今縣道より鐘樓門を望む、志那風の建築にして其構造附近稀に見る所なり、門を入りて左折すれば本堂あり、側に庫裏土蔵あり、境内梅桃杉松等を植ゑ其配合頗る趣あり、周圍には竹林多し、昔時は禅堂衆寮等ありて諸堂を連ぬるに廻廊を以てせりと、本堂は間口八間半奥行六間半庫裏九間半に四間半、土蔵三間に二間半あり、鐘は古色蒼然たり、銘に(鐘銘省略)(市原郡教育會編纂「市原郡誌」より)
寶積寺の周辺図
参考資料
- 「市原市史」
- 「市原郡誌」

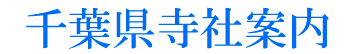
 寶積寺山門
寶積寺山門 寶積寺鎮守社
寶積寺鎮守社 寶積寺本堂
寶積寺本堂