稲荷神社(稲荷町)|千葉市中央区稲荷町の神社
稲荷神社(稲荷町)の概要
稲荷神社(稲荷町)は、千葉市にある神社です。稲荷神社(稲荷町)の創建年代は不詳ですが、日本武尊が東国征伐の際に駒原神社として豊宇受大神を祀ったともいいます。史書によると千葉常兼が大治元年(1126)猪鼻に居館を構え、当社(御達報の稲荷大明神)を、千葉氏の守護神として崇敬、江戸時代には旗本深尾八太夫が当社を復興したといいます。

| 社号 | 稲荷神社 |
|---|---|
| 祭神 | 豊宇気比売命、久久能知命 |
| 相殿 | - |
| 末社 | - |
| 住所 | 千葉市中央区稲荷町2-8-30 |
| 祭日 | 10月15日 |
| 備考 | 旧村社 |
稲荷神社(稲荷町)の由緒
稲荷神社(稲荷町)の創建年代は不詳ですが、日本武尊が東国征伐の際に駒原神社として豊宇受大神を祀ったといいます。史書によると千葉常兼が大治元年(1126)猪鼻に居館を構え、当社(御達報の稲荷大明神)を、千葉氏の守護神として崇敬、江戸時代には旗本深尾八太夫が当社を復興したといいます。
「千葉県神社名鑑」による稲荷神社(稲荷町)の由緒
稲荷神社
「千学集」によると、千葉常兼が大治元年丙午六月一日、御達報(地名)の稲荷大明神を千葉の守護神とする。栄福寺古文書によれば、神職粟飯原某に奉幣の儀を司らせ、社殿の営繕悉く千葉氏が行うとある。千葉氏没落以降は村民がこれを維持した。明治六年粟飯原大蔵神職を辞し、別当寺の冨流山上行院も維新後これを廃寺、現福正寺となる。寛政七年乙卯年に京都伏見稲荷大社より正一位五社稲荷大明神の神号を賜る。現拝殿は安政六年三月の建立。神社由緒書によれば源頼朝が治承四年大刀一振を献上祈願している。(「千葉県神社名鑑」より)
境内掲示による稲荷神社(稲荷町)の由緒
往昔、日本武尊が東夷征伐のため上総国へ赴く際、当地に「御駒(馬)」を放ち、この地主神に夷賊退治の無事達成を祈り誓いを立てた事から、此の地は「駒ヶ原」と呼ばれた(駒原神社再建寄進帳・文政五年)。御社は「駒原神社」として豊宇受大神を祀った。
その後、大治元(一一二六)年、千葉常重が猪鼻に館を構えて以来、千葉氏の守護神として「御達報 稲荷」と称した(千学集)。また治承四(一一八〇)年源頼朝が太刀一振を献上し祈願(神社由緒書)以後社殿の修繕などは代々千葉氏が執り行う。
延宝年間(一六七三〜八〇)に旗本深尾八太夫が復興を図り、日蓮宗上行院を別当寺として当社境内に建立(明治維新後、廃寺)寛政七(一七九五)年、京都伏見稲荷大社より正一位五社稲荷大明神の神号を賜る。千葉氏没落後は氏子が相協力して造営修理に当たり、文政三(一八二〇)年、社殿再建を開始した事や安政六(一八五九)年、拝殿を建立した事などが記録に見える。
御祭神は豊宇気比売命(豊宇気大神)久久能知命。
毎年七月九日、御宝物お虫の儀を行う。
地名の変遷は御達報村から御達浦村、千葉寺村新田五反保、五反保村、五田保村。やがて明治二十二年千葉町大字千葉寺字五田保、昭和十一年より稲荷町に。
境内には当地の偉人、花沢紋十が天保七(一八三七)年、甘藷澱粉製造を始めた事などを記した「甘藷澱粉製造発祥之碑」がある。(境内掲示より)
稲荷神社(稲荷町)の周辺図

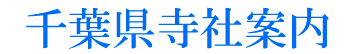
 稲荷神社鳥居
稲荷神社鳥居 稲荷神社社務所
稲荷神社社務所 稲荷神社境内社
稲荷神社境内社 稲荷神社境内社
稲荷神社境内社